「三郎ちゃんごめんね」平元文雄
キリスト教信者で、「塩狩峠」「氷点」「銃口」などの作品で有名な作家、三浦綾子さんが素敵なエッセイ「小さな一歩から」を書かれています。私はその中の「三郎ちゃんごめんね」というお話に心がひかれます。
少し長いですが、全文紹介したいと思います。お読みいただければ嬉しいです。
私は戦時中、小学校の教師を7年間勤めた。私は無器用な質で、リンゴ一つ今もって満足に剝けない人間だ。
それがなぜか三度も小学一年生を受け持っている。元来子ども好きで世話好きなところがあったせいであろうか。
浅原三郎(仮名)はその一年生の中の一人だった。太平洋戦争開戦の翌年、一九四七年、、三郎は母親に手を引かれて学校にやって来た。目のくりっとした、愛らしいがひ弱な体つきだった。三郎は母親の袂の陰から顔をのぞかせ、私と目が合うと、にこっと笑ってまた隠れた。彼は今でいう遅進児だった。自分の名前をようやく読み書きできるだけで、すらすらと読本を読むなどということは、受持っ た一、二年を通して一度もなかった。
幼い時の熱病が、彼の知的な発達を阻害したのかもしれない。他の三人のきょうだいは何れも成績優秀だったから、彼の存在は家人の胸をさぞ痛めたことであったろう。みんな優しいきょうだいたちだった。
三郎は私によくなついた。机間巡視の時、三郎のそばに立つと、彼は鉛筆の芯をなめながら、可愛い笑顔を見せて私を見上げた。私はその三郎のために、極めて容易な質問を準備していき、一日に一度は三郎も級友たちの前で答え得るように気を配った。
彼の家の近くに私の知人の家があって、時折私用でその知人宅に行った。中に入って話をしていると、三郎がそっと細目に玄関の戸を開け、ちょろりと顔を出して は逃げていったりした。そんなある日、雨の中を私は傘を指してその知人宅に向かった。と、向こうから唐傘を指した三郎がやって来た。私を見ると、彼はうれしさのあまりか立ちどまって、傘を地に置き、両手を膝まで下げて、「先生、さようなら」と、挨拶をした。彼の傘はたちまち雨にぬれた。
この光景は、彼の頭を撫でたときの、あの吹き出物の感触と共に、今も忘れ得ない。
私が勤めて七年目、日本は戦争に敗れた。信じていた勝利が惨敗と決まった時、私は虚無的な人間になってしまった。そして三郎たちが四年生を終ろうとする三月、教職を離れた。辞職して間もなく、私は肺結核に倒れた。肺結核は当時、数多くの青少年を蝕んでいた。感染を恐れて、 結核患者のいる家の前を口をふさいで子どもたちは通り過ぎたものだった。そんなわけで、私は生徒からくる葉書にも返事を出さないようにした。それでも年賀状の中に生徒たちの名前を見ることは、何ものにも替え難い幸せだった。しかし、そんな年賀状の中に、三郎の名前を見出すことはできなかった。年賀状をくれる生徒はむろん愛しいが、くれない生徒のことも気にかかった。
年月は過ぎ、三郎たちも進学あるいは就職へと進んでいった。一方、私の上にも年月は流れた。敗戦の翌年に得た肺結核は十三年の療養を必要とした。私をキリストに導き、虚無から立ち上がらせた青年も死に、そして病い癒えた私は三浦光世と結婚した。私はもう三十七歳になっていた。三郎たちと別れて十数年は過ぎ去っていた。
私が小説「氷点」を書いた翌年、思いがけなく三郎から年賀状がきた。右肩上がりの、「浅原三郎」と書いたその字は、小学生の時と全く同じで、たまらなく懐かしかった。友だちの少ない彼は、新聞で私の記事を見るまで、私の消息を知ることができなかったのであろう。年賀状にはこう書いてあった。
「先生、ごぶさたしました。ぼくは三郎です。今、自転車屋に勤めています。毎日がんばっていますから、一度見に来てください」
私は喜んで、すぐに返事を書いた。
「今の仕事が片づいたら、必ずいくからね」
そんな文面だった。私の目に、雨の降りしきる中で、傘を地上に放り出し、ていねいに挨拶をした三郎の顔が目に浮かんだ。私の心の中に、三郎が浮かばぬ日はほとんどなかった。
(あの、ガンベ〈吹き出物〉は治ったろうか)
(あの、か細かった体はどんなふうに成長したことだろうか)
すぐにも飛んで行きたい思いだったが、小説の締切に追われていて、なかなか時間が取れなかった。三郎からの葉書を、私はいつもハンドバックに入れていた。さて、今日は訪ねようと思った日、どうしたことか三郎の葉書がない。
困ったと思ったが仕方がない。三郎と同じクラスの子に尋ねれば、消息はわかるだろうと思った。偶然街角で会った
教え子の一人に、
「三郎ちゃん、どうしてる?」と尋ねると、
「先生、三郎君は、確か今年の春、急性肺炎で死んだ筈ですよ」と言われた。
必ず訪ねて行くから・・・・
その言葉を信じて、三郎は死んだのではないか。以来私は三郎について固く口を閉ざしてきた。三郎は、今も自転車屋の前で、私を待っていてくれるような気がしてならない。
三浦さんが、一人ひとりの子どもをいつまでも心にとめておかれること、三郎くんに対する謙虚な態度に心を打たれました。
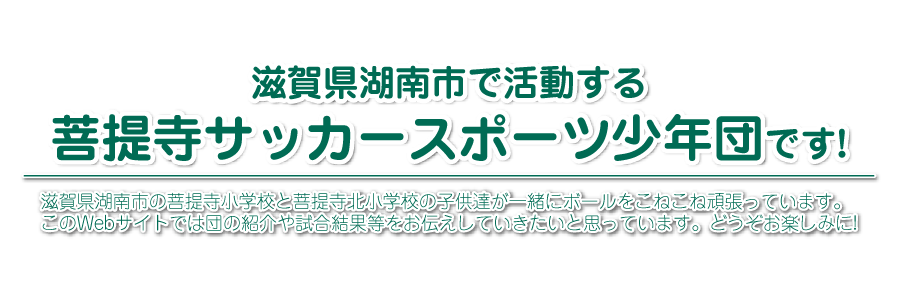

コメントをお書きください